~戦国時代の姫たちの悲しい物語〜
戦国時代の姫君たち、悲劇の物語
戦国時代とは具体的には、1467年の応仁の乱から1615年の大坂夏の陣までを指すといわれています。
その間140年の間に数々の武将や大名が覇を唱え、戦国の露と消えていきました。
そしてその傍らには悲劇の運命に巻き込まれる姫たちの姿がありました。
このページではそんな姫たちのエピソードを4つほど紹介したいと思います。
正室とは?
まず用語について解説したいと思います。
かつて日本の高貴な人の奥さんには、正室、側室という分け方がありました。
正室とは大名、公家などの身分の高い人の本妻のことを指し、また、側室とはそのような人たちの妾のことを指しました。
本妻である正室に子供がいない場合、側室の子供が跡を継ぐこともありました。
祖先の祭祀を絶やさないようにするという儒教の考え方がもとになっているとのことです。
また、継室とは正室がなくなってその後、正式な結婚により迎えられた正妻を指します。
謀反の疑いをかけられ処刑された「瀬名姫」(築山殿)徳川家康の正室

瀬名姫
瀬名姫は徳川家康の最初の正室です。瀬名姫とも呼ばれたりしますが、当時の資料にその記載はなく、
一般的には岡崎に住んでいた場所の名前を取って築山殿と呼ばれています。
1542年に生まれて、1557年に駿府で人質となっていた松平元信(のちの徳川家康、以下徳川家康と表記します。)と結婚します。
桶狭間の戦いで今川義元が討たれたことで徳川家康は今川氏のもとを去ります。それがきっかけで瀬名姫も岡崎に移ることとなります。
この際に、瀬名姫の両親は家康の裏切りに怒った今川氏真によって自害させられてしまいます。
瀬名姫は岡崎城内に住んでいないことから、離縁されたとの見方もあります。両親も亡くなり、故郷も離れたことで、重い運命が瀬名姫にのしかかっている印象を受けますね。
家康の息子、信康の母として岡崎で生活を続けますが、ある日そんな瀬名姫に謀反の疑いがかけられてしまいます。
当時、甲斐を領していた武田勝頼と内通していた信康の家臣、大岡弥四郎らが処刑される事件が起きたのですが、
瀬名姫も謀反に加担していたという疑いがあったのです。
信康の正室の徳姫は、織田信長の娘だったのですが、信長に対して信康や瀬名姫の罪を訴える訴状を信長に送ります。
それがきっかけで信康は切腹、瀬名姫は首をはねられることになってしまいました。
実際に瀬名姫が武田勝頼と内通したなどの情報は、信頼のおける資料からは見つかっておらず、瀬名姫の罪は冤罪だったとの見方があります。
そうだとすると戦国時代の悲しい運命に巻き込まれてしまった瀬名姫の人生に手を合わせたい気持ちになります。
2度、落城する城を見た「お市の方」浅井長政の継室、柴田勝家の正室

通説では1547年に尾張(今の愛知)で生まれたそうです。兄は有名な織田信長です。
「祖父物語」などの江戸時代の資料では天下一の美貌を持っていたと書かれています。
そんな美しい姫、お市の方は2度、自らの居住する城が落ちるさまを見た悲しい運命を生きた人だったのです。
最初、近江の戦国大名、浅井長政の継室となります。
兄である信長は、当時美濃攻略を成功させるために浅井長政と同盟を結ぶこととしました。(長政の長は信長からもらったとの説もあり。)
また北近江を領していた浅井長政と同盟を結ぶことは、尾張の信長としては上洛路を確保するうえでも重要であり、
事実、こののちに信長は上洛を果たしています。
最初、長政との同盟を喜んでいた信長でしたが、事態は金ケ崎で急変します。
信長は越前の朝倉義景を攻めるのですが、その際に浅井長政が信長を裏切るのです。
この裏切りの理由は現在でも謎とされています。
挟み撃ちになるところで何とか信長は金ケ崎を脱するのですが、これを知らせたのはお市の方だったとする話もあります。
その後、姉川の戦いを制した信長は、3年後の1573年に浅井長政の城である小谷城を攻めます。
降伏勧告もしましたが、長政は断り、城内で自害して果てました。
お市の方は信長の家臣により母子ともども救出され命は助かりました。

※お市の方
その後は、信長の兄や叔父の城に身を寄せていたなどいろいろな説があります。
やがて信長が本能寺の変で明智光秀の裏切りにより亡くなり、清須会議という跡目を決める話し合いが清州城内で行われます。
その清須会議でお市の方と柴田勝家の結婚が決まりました。
柴田勝家は信長の譜代の家臣(何代もその家に仕えていること)で、信長の家臣の中では大変力を持っている人でした。
かつて城内でお市の方を見る機会もあったでしょう、信長の妹と結婚するということは勝家としてはうれしかったのではないでしょうか。
しかし、運命は残酷で、この2人にも別れの時が来ます。
織田信長が行っていた天下布武を誰が引き継ぐのか、それはいずれはっきりさせないといけないことでした。
抜け目なかったのは羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)です。
1583年に賤ケ岳で行われた戦いは、柴田勝家と秀吉の雌雄を決するものでした。この戦いに敗れた柴田勝家は越前の北ノ庄城という自分の城に逃げ帰りました。
この城も秀吉によって包囲されますが、落城を悟った柴田勝家はお市の方に逃げるよう諭しますが、お市の方は拒否します。
ともに自害する道を選ぶのです。
そして城に火がはなたれ、燃える城でお市の方は亡くなってしまいました。

大きすぎた権力に惑わされた「淀殿」豊臣秀頼の母
淀殿は上述したお市の方の娘です。本名は浅井茶々。
1569年に小谷で生をうけます。小谷城落城後、お市の方と共に脱出、その後の経過は上述した通りです。
北ノ庄城の戦いでお市の方と柴田勝家は自害しますが、淀殿は脱出したとされています。
その後のことはいろいろな説がありますが細かいことはよくわかっていないらしいです。
1588年ころ、秀吉の側室となります。
淀殿の名は、秀吉からもらった山城淀城がもととなっているそうです。
秀吉はなかなか子供に恵まれず、秀頼の誕生を喜びました。
豊臣家の死後、後継者の秀頼の母であった淀殿は豊臣家内の政治を牛耳るようになります。
淀殿は小説などであまりいい書き方をされないことがあります。
それは、大坂の陣での失策が尾を引いているのでしょうか。
大坂の陣は、冬の陣、夏の陣の2つに分かれます、江戸幕府を開いた徳川家康と、そのあとも有力大名として大阪にいた豊臣秀頼との天下をニ分する争いでした。
家康からしたら天下統一の総仕上げといった感じでしょうか。
京都、方広寺の鐘の事件をきっかけとして大坂の陣が勃発します。(いまでもその鐘は方広寺に行けば見ることができます。)
豊臣家の当主だった豊臣秀頼でしたが、実際に権力を握っていたのは淀殿でした。
当時、天下には豊臣家側の大名家や武将が没落したことで、巷に浪人があふれていて、
大阪には再起を図ったそんな者たちがたくさん詰めかけました。
有名なところでいうと、真田信繁(幸村)、塙 団右衛門(ばん だんえもん)などの人物たちがいます。

浪人の数もものすごく、優秀な人材もいたので最初、勝敗はわからないといわれました。
特に、真田丸での真田幸村の活躍は有名ですよね。
しかしやはり徳川家の力はすさまじく、士気を高めるため大阪方の武将たちは秀頼に出馬を乞いましたが、秀頼は戦場に姿を現しませんでした。
それは、淀殿が秀頼が戦場に出ることを嫌ったからだという話があります。
そして史上有名な失策を淀殿はしてしまったといわれています。それは冬の陣で講和をする際に、大阪城の堀を埋めてしまったのです。
堀というのは城の周りを囲む穴のようなものですが、それは城にとって防御のかなめともいえるほど重要なものでそれを埋めてしまうのは前代未聞のことでした。
周りは反対したそうです。しかし堀は埋められ、結局それがきっかけでその後に行われた夏の陣では、大坂城は落城することとなるのです。
堀を埋めて、講和をしてしまった理由としては城内に大砲を撃ち込まれたことがきっかけだったといわれています。
その爆音は淀殿に講和を決意させました。
このように淀殿は三大悪女にも数えられている女性ですが、ただ、悲運の女性とも思えます。
考えてみれば淀殿の幼少期はお市の方と共にいて、2度の落城を経験しました。
きっと戦で身内がなくなる恐ろしさなどがトラウマになっていたのではないでしょうか。
そういった意味では淀殿も歴史の被害者だったのかもしれません。
徳川と豊臣、二大勢力にはさまれた「千姫」豊臣秀頼の正室
千姫は1597年に生まれます。父親は江戸幕府2代将軍徳川秀忠、母親はお市の方の娘お江です。
7歳の時に豊臣秀頼と結婚し、大阪城に入ります。
歴史的展開を見ればわかることですが、豊臣家と徳川家の関係はきわどいところがあり、
1603年に大阪に入ったのですが、西軍と東軍が分かれて戦った関ヶ原の戦いが1600年なので
いわば政略結婚のようなかたちだったと思います。
当時としては珍しいことではなかったのかもしれませんが、わずか7歳で政治の道具として利用されてしまうなんて悲しい話ですね。
1615年の大坂夏の陣で、大阪城が落城します。
千姫の命も危ないところでしたが、何とか生き延びることができました。
12年過ごした大阪城が落城するさまをどのように感じていたのでしょうか。
秀頼と淀殿の助命を願い出たそうですが、その願いが聞き届けられることはありませんでした。
そのあとは、本田忠刻(ただとき)と結婚し、桑名城や姫路城などで暮らしたそうです。
しかし、そんな本田忠刻も早くに亡くなり、出家して天樹院と名乗ったそうです。
江戸城に入り、竹橋御殿という今の竹橋御門の近くで静かに暮らしたそうです。
在りし日を振り返っていたのでしょうか。
徳川家光からは大事にされたそうで、後半生は幸福だったのではないでしょうか。
※千姫に関しては別の記事も書いているのでよかったらどうぞ。
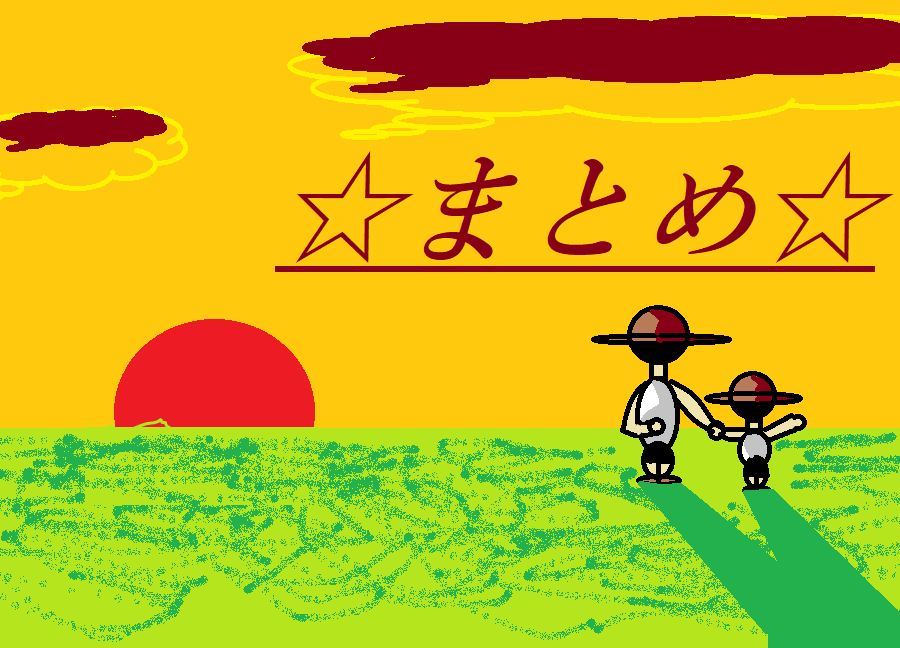
以上、戦国時代の姫に関する悲しいエピソードでした。
参考になれば幸いです。
お読みいただきありがとうございました。
〜関連する記事〜
