桃太郎の発祥は岡山じゃない?桃太郎伝説の謎

桃太郎とは?
言わずと知れた日本のおとぎ話の代表的存在です。おじいさんが川で拾ってきた桃から生まれた桃太郎は、猿、犬、雉の仲間を引き連れて鬼ヶ島へ鬼退治に向かいます。
その発生は平安時代、または室町時代後期から江戸時代前期だともされ、現在残っている文献で最古のものは、赤本(寛文期に始まる子供向けの本)の「もゝ太郎」だそうですが、
かつて研究されていたものとしては、元禄以前の「桃太郎話」などもあったそうです。(現存していない。)
発祥の地は諸説あり、香川県、愛知県、山梨県などいろいろありますが、
戦後では岡山が有名となりました。
現在では絵本などで描かれるように、川を流れてきた桃の中から桃太郎が生まれてくるという形式が一般的ですが、
江戸時代では、川を流れてきた桃をおじいさんとおばあさんが食べて若返り、桃太郎を産むという話が主でした。
また、各地で伝えられている伝説にも多種多様なものがあり、
その分布は一定していません。
と、このように桃太郎という物語は非常に興味深い謎を多く含んでいる物語なのです。
この記事ではそんな桃太郎にまつわる謎を紹介し、かつてより論争となっている
桃太郎の発祥地はどこなのかという問題についても整理していきたいと思います。
さて、かつてより桃太郎などの昔話を研究することは民俗学などの分野で行われていました。
まずは柳田国男の「桃太郎の誕生」から行きたいと思います。
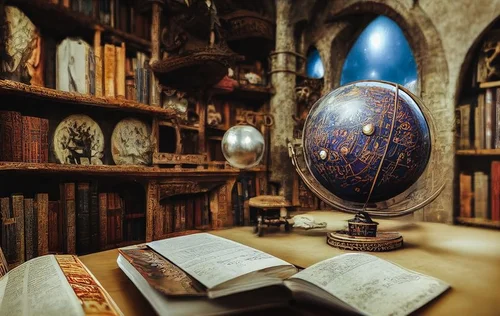
柳田国男「桃太郎の誕生」~神話とのつながり
柳田国男(1875~1962)は日本の民俗学の草分け的存在です。
岩手の伝説などを採録した「遠野物語」はとても有名ですね。
ほかにも「日本の伝説」や「蝸牛考」他、数多くの著作を残しています。
柳田国男は昔話の研究をとても重要視していました。
昔話は古くは神話から派生したものだとも考えられていました。
そんな昔話にかつての日本人の考え方、思考を読み取ることができると考えたからです。
そんな柳田国男が記したのが「桃太郎の誕生」です。

この本では、桃太郎に限らず一寸法師や瓜子姫などの昔話について、
非常に明晰な考察をしています。
この本の中には”小さ子”という観念が登場します。
桃太郎もその”小さ子”の内の一人です。
日本神話には、少名毘古那神(すくなびこなのかみ)と呼ばれる神様が登場するのですが、
この神様がとても小さい神様なのです。
”小さ子”の原型と考えられ、
一寸法師などの昔話に影響を与えたのでは?ともいわれます。
桃太郎という話は神話にルーツがあるのかもしれません。

世界の昔話との類似
世界に目を向けてみると、桃太郎の話も一層興味深いものとなってきます。
桃太郎のように果実から生まれる主人公という形式は世界的にはあまりないそうなのですが、
主人公が何かの試練を乗り越えるという形式はよくあります。
英雄譚というやつですね。
ギリシャ神話にはヘラクレスの12の試練という話があります。
毒を持つヒュドラという蛇や、首が3つもあるケルベロスという犬の退治など
とても常人にはできない試練を与えられ、それを達成しています。
桃太郎を世界に分布する神話の一形式ととらえると、慣れ親しんできた桃太郎の話の
見方も随分と変わってくるのではないでしょうか?
青年が冒険に出て、何かの試練を達成し、故郷に戦利品を携えて帰還する、
こういう話は探せば結構あるものです。
桃太郎は英雄だったのか?
さて、話は変わりますが2013年度「新聞広告クリエーティブコンテスト」というコンテストで
最優秀賞を受賞した「めでたし、めでたし?」という広告がとても話題になりました。
この広告は「ぼくのおとうさんは、ももたろうというやつに殺されました。」と書くことで、
正義というのは視点によっては全然変わることだということを我々に気付かせてくれます。
昔話になるときは、”鬼が悪者だった”と描かれたり、描かれなかったりしますが、
鬼が特に悪い奴だという描写がない場合は、桃太郎は略奪者であり、破壊者ですよね。
(昔、トリビアの泉で唱歌「ももたろう」の5番の歌詞が怖いと紹介されたことがあります。
鬼退治をおもしろい、おもしろいとうたっているのです、怖いですね。)
桃太郎の話が世界の神話をルーツとしていると考えるとやっぱり鬼は特に悪い奴ではなかったのかもしれませんね。
世界史を見るに、アレクサンドロス大王やカエサルなど、他国を侵略し自国を拡大した人は
英雄と呼ばれますから。

鬼はいたのか?各地に残る伝説と証拠
桃太郎と言えば、お供の犬、猿、雉が有名ですが、
これは干支の考え方が影響していると考えられています。
十二支は方角に対応しているのですが、不吉な方角に鬼門というものがあります。
鬼門=鬼と考え、その反対にある干支の申、戌、酉をお供にしているのでは?と言われています。
桃太郎の話の成立にはいろいろな要素が加わっているんですね。
また、鬼という言葉の語源は”隠ぬ”であり、見えないものを意味する言葉でした。
鬼と言えば鬼の角をはやして、トラ柄のパンツをはいているイメージですが、
これも鬼門の方角が丑と寅だからで、十二支の影響が考えられます。
要するに姿かたちは想像なわけです。
鬼は歴史上、日本列島に存在しなかったのでしょうか?
残念ながらいなかったという可能性の方が高そうですが、
いたとする証拠はいくつかあります。
まず、各地に残る鬼の遺骸と伝説です。
岐阜県和良町の念興寺には、鬼のどくろが祀られています。藤原高光(ふじわらたかみつ)という人が瓢ヶ岳(ふくべがたけ)に出た鬼を退治した際に切り落としたものだそうです。
また、大分県宇佐市にある十宝山大乗院には鬼のミイラがあります。
真偽はわかりませんが、そういうものが各地には残っているわけです。
また、古代の日本の様子を記した日本の正史である日本書紀には鬼と思われる存在を記した
記述が存在します。
欽明天皇5年の項に、佐渡島の北の方のみなべという所に来た存在は地元の人たちに鬼であるとうわさされたそうです。(ただ、北方民族である”みしはせ”であると書いてあります。)
また、平安時代後期の「玉葉」にも伊豆国に鬼が漂着し、島の人を殺害し逃亡したとの記述が存在します。
玉葉は公家、九条兼実の日記で、当時の時代を知る、基礎資料と位置付けられています。
そんな文献に鬼の存在が描かれているのですね。
生物学的に鬼という生物がいたと考えることは難しいと思いますが、
鬼が当時の人たちにとって自分たちとは異なる存在、異文化の人や(事実、日本書紀の鬼はみしはせであったと書いてあります。)
自分たちとは違う価値観の存在、盗賊や犯罪者であるととらえると可能性は高まってくると思います。
自分たちとは異なる恐ろしい存在を鬼と呼んだのかもしれません。

桃太郎の発祥の地はどこ?そのモデルとは?
鬼と呼ばれる人がいたのなら、桃太郎のような人物も実際にいたのかもしれません。
後述するように、桃太郎の発祥地を自称する地の人は
特定の人物を桃太郎のモデルに挙げていたりします。
長年、論争の的となっているのが桃太郎の発祥の地です。
有名どころは岡山ですよね、日本遺産にも登録されています。
実は桃太郎の発祥地を自称する県は他にもあります。
山梨県、香川県、愛知県などが有名です。
これらの件は、観光資源として桃太郎を利用しようとして
発祥地を自称したといういきさつがあります。
では、実際どこが本当の発祥地なのでしょうか?
これは私見ですが、それを確定することは容易ではないと思います。
やはり古い話ですし、話自体も時代を経て変わっていると考えられるからです。
成立した時代も定かでない以上、これという答えを出すことは難しいと思います。
しかし、かつてより人々はその物語に魅了され、あくなき探求心で
桃太郎の発祥地を特定しようと努力してきました。
ここではそんな、桃太郎発祥地をいくつか紹介し、
最後に管理人の思う発祥地を提示したいと思います。
桃太郎発祥地①岡山県
現在、岡山が発祥地として有名ですよね。

岡山説は難波金之助というか人が昭和5年に桃太郎の史実という本で主張したもので、
温羅(ぬら)を征伐した吉備津彦命を桃太郎のモデルとしています。
桃太郎岡山発祥説は日本遺産に認定され、世間的にも発祥地ということになっていますが、
吉備津彦命の話はとても古い話で、
桃太郎が生まれたんじゃないかとされる室町時代よりはるかに前です。
吉備津彦、黍団子の関係性も主張されますが、
こじつけのようにも思われます。
温羅のいた城は鬼ノ城と呼ばれ、いかにも鬼がいましたといった名前ですね。
これらの話は日本書紀に出てきます。
また、岡山にはそれらの伝説ゆかりの地もあります。
桃太郎発祥地②香川県
香川県高松市にある女木島は別名鬼ヶ島と呼ばれています。
言わずもがな、桃太郎に出てくる鬼ヶ島ですね。
高松市内には鬼無という地名があり、これは桃太郎が鬼を退治して鬼がいなくなったからだとされています。
女木島には大洞窟があるのですが、いかにも鬼がいたような感じがする場所です。

また、桃太郎神社なるものもあり、
そこには桃太郎、犬、猿、雉のお墓が建っています。
香川の桃太郎伝説では吉備津彦命の弟である、稚武彦命(わかたけひこのみこと)が桃太郎のモデルだとされています。
桃太郎発祥地③山梨県
山梨県大月市には古くから桃太郎伝説があったそうです。
おばあさんが洗濯をしていた川は桂川で、ももくら山から流れてきた桃から
桃太郎が生まれたそうです。
ここまではよく知っている桃太郎の話ですが、ただ、山梨伝説で桃太郎が鬼退治に行くのは鬼ヶ島ではなく岩殿山という所です。
鬼の石杖という物のほか、各地に伝説の名残が残っています。
桃太郎発祥地④愛知県
愛知県犬山市には、桃太郎伝説を今に伝える桃太郎神社があります。
そこにはユニークな桃太郎にまつわる像がたくさんあり、来た人を驚かせます。
コンクリート像は浅野祥雲さんという天才コンクリート像製作者がつくった像で、
神社は愛知の珍スポットと言われています。
宝物館には桃太郎にまつわるいくつかの品が納められていて、
そこには鬼の金棒や、かつて存在した鬼のミイラや桃の化石の写真がおいてあります。
発祥地は・・・

岡山説は戦前は、香川説などに後れを取っていました。
しかし、現在では岡山説が主流となっています。
では、本当の発祥地とはどこなのでしょうか?
現状では、資料が少なくて判断のしようがないと思います。
正直、自分の信じたい説を各々が信じるという形しかないのではないでしょうか。
そのうえで、自分は香川の説を推したいと思います。
やはり、鬼のいた地は島なので、女木島は鬼ヶ島のイメージにぴったりだと思うからです。
ということで当サイトでは、桃太郎=稚武彦命ということでこの記事を終わらせていただきたいと思います。
お読みいただきありがとうございました。