方広寺の大仏~東大寺の大仏より大きかった太閤秀吉の作った大仏
かつて京都にあった巨大な大仏は、天下人太閤秀吉の作らせたものでした。
どれくらい大きかったのか、どうして作られたのか、どうしてなくなってしまったのかその謎を追います。
方広寺とは
方広寺は京都は東山区にある天台宗の古刹です。秀吉が作らせた大仏を安置するための寺として創建されました。
この寺の鐘の銘(鐘に書いてある文字)が引き金となって大坂の陣が勃発したことでも有名です。
(この鐘は現在も見ることができます。)
隣には豊国神社と呼ばれる秀吉を祀る神社があり、こちらにも観光客がたくさん訪れます。
見どころは宝物館の秀吉の歯だったり、伏見城から移された唐門だったり、名刀の骨喰藤四郎なんかも見れちゃいます。
また、近くには三十三間堂などもあるので、一緒に行くのもいいところです。
さて、そんな方広寺ですが前述したようにもともとは秀吉の作らせた大仏を安置するためのものでした。
しかし、今はその大仏は寺にありません。
どういうことでしょうか、そもそもその大仏とはどのようなものだったのでしょうか。
東大寺の大仏より大きかった方広寺の大仏
天正14年(1586年)秀吉は松永久秀によって消失してしまった東大寺の大仏に代わる巨大な大仏を京に作ろうと考えていました。
かつて京には、足利義教の命で作られた雲居寺(うんごじ)の大仏など東大寺の大仏に並ぶ大きさを誇る大仏があったのですが、
そちらも応仁の乱などで焼失していました。
どこに作るかは紆余曲折あったのですが、結局現在、方広寺があるあたり現在の東山区のところに決まりました。
実はそこにはすでに佛光寺や瀧尾(たきお)神社などの宗教施設があったのですが、それらも寺の創建にあたり移動させられてしまいました。
天正16年(1588年)に大仏殿の造営が始まります。
それらは民衆を巻き込んだ派手なものだったようです。
また、大仏殿造営に当たり木材を各地の大名から募り、島津義弘は屋久島から屋久杉を贈ったそうです。
その屋久杉を切った株は、ウィルソン株として今に伝えられています。
またこの時、同時に歴史上有名な政策が行われました。
刀狩りです。
これは大仏や鐘を作るための材料という名目で刀類がさかんに徴収されました。
方広寺の大仏と刀狩りにこんな関係があったんですね。
大仏は初代から四代まで作られました。
秀吉の時代の初代は木造で作られたそうです。東大寺の大仏は金銅仏でしたね。
そんな過程で制作された大仏でした。
大きさは約19mもあったとされていて、当時としては最大のものでした。
しかし、それは比較的早い段階で崩壊してしまいます。いったいどのようなことが起きたのでしょうか?
それは戦国の世に起きたとある自然災害が関係しています。
伏見大地震で崩れた大仏
文禄5年(1596年)にそれは起きました。
歴史上、慶長伏見大地震と呼ばれるものです。
震度は6ほどで、死者は1000人程度でたとされます。
この地震で伏見城天守ほか、京にある天竜寺なども倒壊したそうです。
そして方広寺の大仏も倒壊してしまいました。
「義演准后日記」に崩壊の様が書かれているそうです。義演は戦国時代の真言宗の僧です。
手が落下し、全身にひび割れが起きたとされます。
このころはまだ秀吉も存命だったのですが、この地震についてある逸話が残っています。
「朝鮮太平記」にその記述があるそうです。
それは、大仏の眉間に矢を射かけるというものです。
理由としては国家安泰のために大仏を安置していたのに、その大仏自身が災害で倒壊するとは
何事か!ということでした。
この世の栄華を極めた秀吉でも地震はさすがにどうすることもできない
そんなもどかしさを大仏にぶつけたのでしょうか?
大仏からしたら八つ当たり以外の何物でもないですね。
その後、善光寺の仏像が移された?
これは余談ですが、今の長野の善光寺の本尊の
信濃善光寺如来が方広寺に移されていた時期があるそうです。
伏見地震で倒壊した大仏の代わりとして移されたそうです。
もともと、戦乱のさなか善光寺如来は武田信玄によって
善光寺から甲斐善光寺に保護を名目として移されていました。
(善光寺のある場所は史上有名な川中島の近くにあり、川中島の戦いの舞台となりました。)
そういう経緯があったので、京にもってくるのも大丈夫だと思ったのでしょうか。
善光寺の本尊は日本最古の仏像と伝えられる大変、ありがたいもので。
本尊は絶対秘仏なのですが、今でも善光寺には全国から参詣者が絶えません。
そんな善光寺如来は倒壊した大仏の代わりになると思われたのでしょう。
この時、件の大仏は役立たずと言われ粉々にされたとされる話も伝わっています。(宣教師ゴーメスの書簡)
ただ、この善光寺如来は少し怖い話がありまして、この仏さまを移した者はたたられるというのです。
この仏像を移した武田氏や織田氏はその後滅亡してしまいました。
そして善光寺如来を方広寺に移した数年後、秀吉も不治の病にかかってしまします。
世の人は噂しました祟りが起こったのだと。
そして秀吉の死の前日、信濃に返されることが決まりました。
少し不思議な話なので、ここで紹介しました。
方広寺造営は仏教勢力対策だった?
戦国時代は恐ろしい時代で、人々が武器を取り戦いました。
それは農民でも例外ではなく、一向一揆などは大名を滅ぼすほどの勢力を誇りました。
また、宗教勢力も僧兵などの武力を持ち、大名を脅かしました。
織田家バーサス一向宗の争い、石山合戦などは史上有名ですね。
また、織田信長の比叡山焼き討ちなども宗教勢力への締め付けだったとされます。
室町時代の比叡山はかなりの発言力を持っていて、朝廷や将軍に圧力をかけたこともあったそうです。
また天文法華の乱では当時法華宗と呼ばれた、日蓮宗の寺を焼き討ちにしたりしています。
また石山に本願寺が移ったのは、京の寺が法華宗に焼き討ちされたことが原因でした。
宗教勢力も相争っていたのです。
方広寺造営はそうした宗教勢力対策だったとする説もあります。
方広寺境内にあった妙法院の経堂で各宗派の僧を招いて
千僧供養を行ったのです。言葉の通りたくさんの僧を招いて供養するものです。
実際は800人だったそうですが、天台宗、真言宗、律宗、禅宗、浄土宗、浄土真宗、時宗、日蓮宗
などから100人ずつ僧が出てきたそうです。
相争っていた各宗派の僧を共同で動かすことによって、争いを収めようとしたのでしょうか。
天下は収まったとするアピールだったのかもしれません。
まとめ
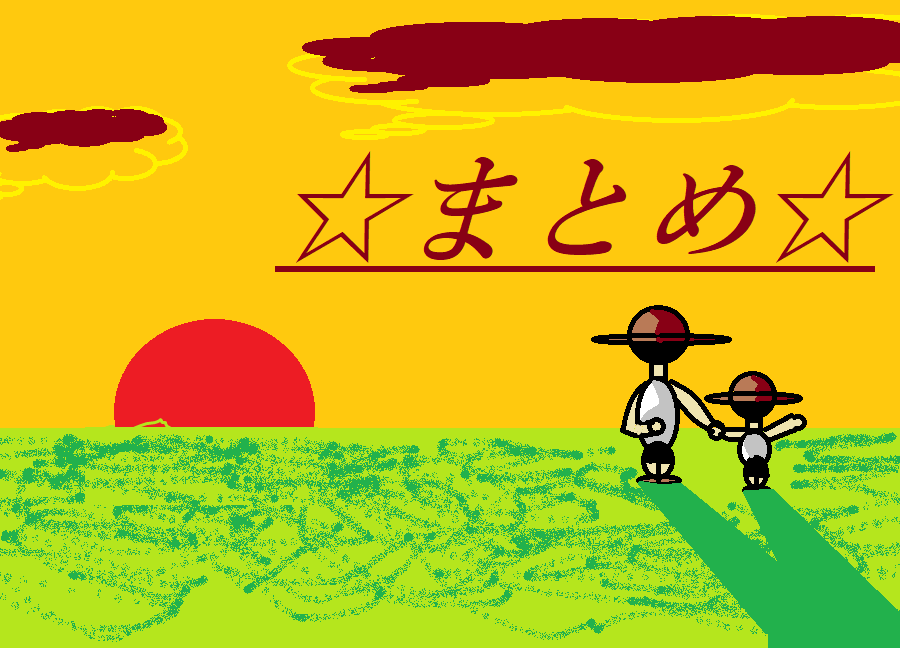
かつて京にあった秀吉の大仏を紹介しました。
東山区にある方広寺を訪ねて、今はなき大仏に思いをはせてみるのもいいかもしれません。
お読みいただきありがとうございました。